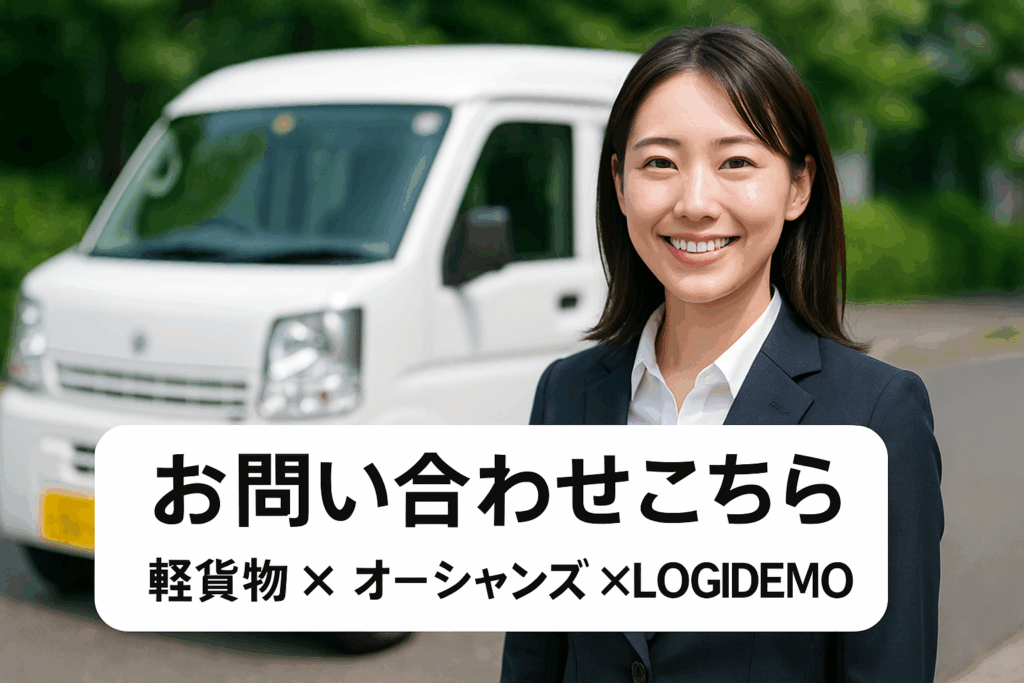News
新着情報&お知らせ
- 軽貨物ドライバー 2025.07.01
軽貨物メンテナンスの基本とコツ|エンジンオイルからタイヤ点検まで

こんにちは!東京都でカスタマイズ型配送サービスを提供する、株式会社オーシャンズです。
近年、物流業界において存在感を増している「軽貨物配送」。この軽貨物配送を営む上で、この記事では軽貨物配送ドライバーさんに向けた豆知識情報やお得な情報を発信しドライバーさんが軽貨物配送業を成功させる手助けになってくれたらと思ってます。長距離・中距離で地方に行った際の現地のグルメ情報もUPしていきます!
この記事では、軽貨物配送の基本から、ビジネスにおける具体的な活用メリット、そして導入を成功させるためのポイントまでを詳しく解説していきます。
「軽貨物のメンテナンス、後回しにしていませんか?」
日々走行距離が伸びる軽貨物配送業において、車両の定期的なメンテナンスはビジネスの生命線です。
本記事では、エンジンオイル交換・タイヤ点検・バッテリー確認など、配送ドライバーが押さえるべき整備の基本と、コストを抑えて安全を確保する実践的な整備ノウハウを網羅的に解説します。
東京都を拠点に軽貨物サービスを展開する株式会社オーシャンズが、初心者でも実践できる車両管理のポイントをお届けします。
軽貨物配送における車両メンテナンスの重要性
軽貨物配送業において、車両の状態は業務品質と安全性を左右する最も重要な要素の一つです。毎日長距離を走行する車両は、その分だけパーツの摩耗や不具合のリスクが高まります。配送業務を安定的に遂行するためには、日常的な点検と定期的なメンテナンスが欠かせません。
配送業務と車両トラブルの関係
車両トラブルが発生すると、予定していた配送ルートや納品時間に影響を及ぼし、信頼失墜・顧客離れのリスクが生まれます。特に個人事業主として軽貨物を営む場合、車両トラブルによる損失は直接的な収入減に繋がります。
そのため、エンジン・ブレーキ・タイヤ・ライトなどの基本的なコンディションは常に良好に保つことが求められます。
整備不良によるコスト・リスク
整備を怠ることによって発生する問題は、単なる修理費用だけにとどまりません。
- 燃費の悪化による燃料コストの増加
- 重大事故や道路交通法違反による罰則・賠償責任
- 稼働停止期間による機会損失
これらのリスクは、事前の点検や軽整備で回避できるものが多いのです。特に定期点検や法定整備を怠ると、保険の適用外や車両の資産価値低下にもつながるため、早期対応が必要不可欠です。
基本の点検手順—毎日・毎週チェックすべき項目
日々の配送業務に支障をきたさないためには、軽貨物車両の状態を常に把握することが重要です。特に軽貨物は過走行気味になりやすく、小さな異常も大きなトラブルへと発展しがちです。ここでは、日常点検・週次点検の項目を明確にし、チェックリスト形式で習慣化する方法を紹介します。
エンジンオイルの量・状態チェック
エンジンオイルは車両の「血液」ともいえる存在です。
毎朝の出発前にボンネットを開け、オイルゲージで量と色を確認します。
以下が簡易チェックポイントです:
- 量:オイルゲージの「F」と「L」の間にあるか
- 色:透明感のある琥珀色であれば正常。黒ずみや金属臭があれば交換検討
推奨交換頻度は3,000〜5,000kmまたは3ヶ月ごとですが、配送頻度が高い方はさらに短く設定しましょう。
タイヤ空気圧・溝・偏摩耗点検
タイヤの状態は燃費やブレーキ性能に直結するため、こまめなチェックが不可欠です。
- 空気圧:各車種指定のkPa(空気圧)を確認し、減少があれば補充
- 溝:スリップサイン(残り1.6mm)に達していないか
- 偏摩耗:片側だけすり減っている場合はアライメント調整が必要
最低でも週1回はすべてのタイヤを確認しましょう。
バッテリー・電装系確認ポイント
バッテリーの不調は、エンジン始動不能や電装トラブルの原因となります。
- エンジンのかかりが悪い、セルモーターの回転が弱い
- ヘッドライトの明るさが通常より暗い
- バッテリー液がMIN以下になっていないか
月1回は電圧計での測定(12.5〜13.0Vが理想)をおすすめします。
1,000kmごとの定期整備ガイド
軽貨物車両は日常的に長距離を走行するため、走行距離に応じた定期整備が不可欠です。特に「1,000km」を目安にすると、部品の摩耗や汚れを未然に対処でき、結果的に車両寿命の延長・故障リスクの低減につながります。以下では、1,000kmごとに行うべき主要な整備項目を具体的に紹介します。
エンジンオイル&フィルター交換時期
オイルとオイルフィルターの同時交換は、エンジン内部を清浄に保つ上で極めて重要です。
- オイル交換目安:3,000~5,000km
- フィルター交換目安:オイル交換2回につき1回
配送業務でアイドリング時間が長い車両は、通常より劣化が早く進むため、1,000〜2,000kmごとの点検をおすすめします。
ブレーキパッド・ローター点検方法
ブレーキは安全運行における最重要パーツです。ブレーキの利きが悪いと感じたら、すぐに点検を行いましょう。
- ブレーキパッド厚さ:3mm以下なら即交換
- ローターの摩耗:段差がある、ひび割れが見える場合は整備工場で診断を
また、ブレーキ液(フルード)の量や色も確認し、2年ごとの交換を推奨します。
ワイパー交換・エアコンフィルター清掃
視界確保や車内環境の維持にも気を配りましょう。
- ワイパーゴム:ビビリ音・拭き残しがあれば交換目安
- エアコンフィルター:花粉や排ガスを多く吸う都市部では、6ヶ月ごとの交換が理想
これらはDIYでも簡単に対応可能な項目であり、費用対効果の高い整備作業です。
整備コストを抑える工夫&DIYメンテ
軽貨物ドライバーにとって、車両整備にかかる費用は避けられない固定コストです。しかし、必要な整備を見極めて適切にDIYや外注を使い分けることで、出費を最小限に抑えることができます。ここでは、費用対効果を重視した整備管理の実践方法をご紹介します。
DIY可能な作業とその注意点
整備の中には、工具と基礎知識があれば自分で対応可能な項目も多数存在します。 代表的なDIY項目:
- エンジンオイル・フィルター交換
- ワイパーゴムの交換
- バッテリー交換(メモリーバックアップ必須)
- ライト類(ヘッドライト、ウインカー)の交換
ただし、ブレーキやサスペンションなど安全性に直結する部位は専門業者に任せるのが賢明です。DIY前には必ず整備マニュアルや車種別解説動画で事前学習を行いましょう。
地域別おすすめ整備ショップ(東京都含む)
費用を抑えたいがDIYに不安がある方には、価格と技術力のバランスが取れた整備工場の活用が有効です。 東京都内でおすすめの整備業者例:
| 店舗名 | エリア | 特徴 |
|---|---|---|
| 車検のコバック 中野弥生町店 | 中野区 | 軽貨物車両対応の低価格車検・整備メニュー |
| イエローハット 三鷹店 | 三鷹市 | バッテリー・タイヤ即日交換サービスあり |
| スーパーオートバックス 東雲店 | 江東区 | 高性能パーツの取り扱い・待合環境充実 |
スペアパーツ購入のコツ・選び方
部品代を節約するには、オンラインショップやリサイクルパーツの活用が効果的です。
おすすめの購入先:
- モノタロウ(汎用整備パーツ)
- 楽天市場・Amazon(正規部品も多数掲載)
- ヤフオク・メルカリ(中古パーツ)
注意点として、必ず車両型式と適合情報を確認し、保証付きの信頼できる出品者を選びましょう。
トラブル時の対処法&緊急整備マニュアル
どれだけ定期的にメンテナンスを行っていても、配送中に突発的なトラブルが発生する可能性はゼロではありません。特に長距離や深夜配送では整備工場が営業していない場合も多く、自力での初期対応能力が問われます。ここでは、よくある緊急トラブルとその対処法を具体的にまとめます。
高速道路・深夜配送中の応急措置
高速道路上での故障は、命に関わる重大事故に繋がる可能性があります。
- 車両をできるだけ路肩へ寄せる
- 発煙筒と停止表示板を必ず使用(設置義務)
- 安全を確保した上でJAFまたは保険会社のロードサービスへ連絡
深夜で工場が閉まっている場合も、24時間対応のロードサービスは多いため、連絡先は常に車内に携帯しておきましょう。
ロードサービス活用のポイント
万が一の際に頼りになるロードサービスは、自動車保険に付帯している場合が多く、内容を確認しておくことが重要です。 ロードサービスで対応可能な主な内容:
- バッテリー上がり対応(ジャンプスタート)
- スペアタイヤへの交換
- 鍵の閉じ込み開錠
- ガス欠時の燃料補給
自動車保険会社ごとのサービス内容に差があるため、契約時に「搬送距離」「無料範囲」「対象車種」などを必ず確認しておきましょう。
故障を未然に防ぐ日常チェック法
故障の大半は事前の点検で予測・防止が可能です。以下は特に見落としやすいが重要な点検ポイントです:
- ラジエーター液(冷却水)の量と色
- タイヤのネジ(ナット)の締まり具合
- エアコンの効き・異音の有無
- バックランプ・ブレーキランプの点灯確認
配送業務前後の10分チェックを日常に取り入れることで、長期的には大きなコスト削減と信頼性向上につながります。
車両メンテナンスの質が、軽貨物配送ビジネスの信頼と安全を支えます。
「整備知識に自信がない」「整備先が見つからない」「もっと効率的に整備したい」——そんな悩みをお持ちの方へ。
株式会社オーシャンズでは、軽貨物ドライバー向けの整備サポート情報や提携整備業者の紹介も行っています。
今すぐ整備効率を改善したい方は、ぜひ以下よりお問い合わせください。