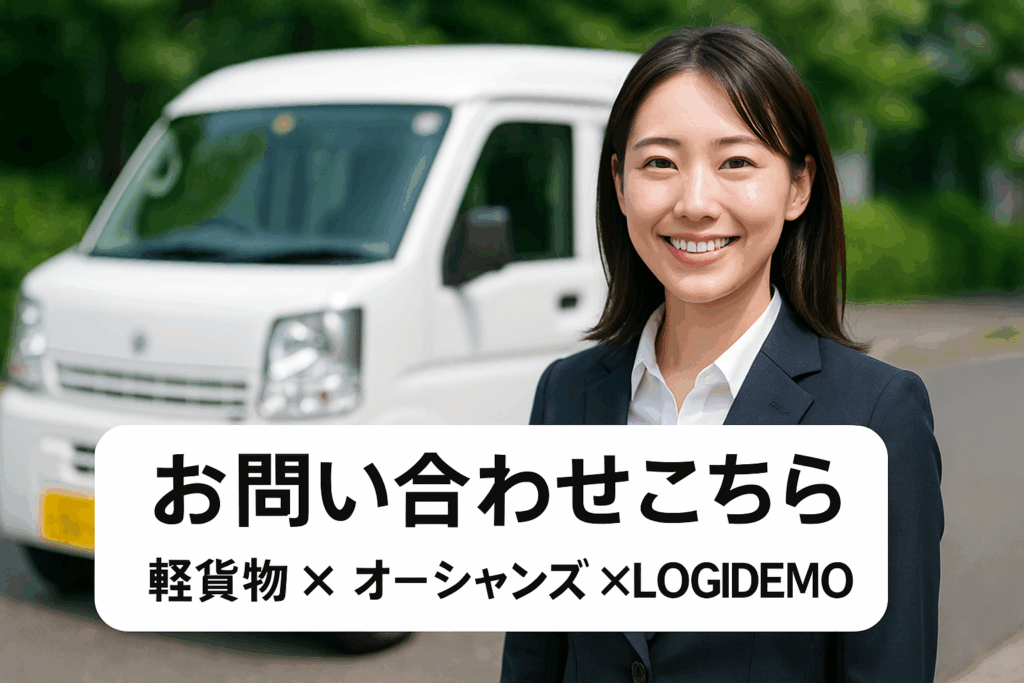Blog
オーシャンズ軽貨物配送blog
- 東京⇔地方都市配送 RELAY便 2025.08.05
東京⇔地方配送を社員でやるべきか?軽貨物委託のコストと効率を徹底比較

「その配送、わざわざ自社ドライバーで毎日運ばなければいけない理由はありますか?」
東京と地方都市部間の定期輸送を社内ドライバーで行っている企業にとって、車両維持費・人件費・雇用リスクは大きな負担となりがちです。
今、多くの企業が軽貨物配送へのアウトソーシングに切り替えることで、配送コスト削減と業務の柔軟性確保を同時に実現しています。
本記事では、東京⇔地方都市間での「自社配送」と「軽貨物委託」の違いを徹底比較し、固定費の見直し・雇用リスクの最小化・配送効率の最適化という観点から、導入すべき理由と具体的な事例をご紹介します。
物流担当者の方必見!
今こそ「その配送、本当に自社でやるべきなのか?」を見直す絶好のタイミングです。
東京⇔地方都市部の配送を「社員」で行うリスクとは?
自社の社員ドライバーによる定期輸送は、一見すると安定した配送体制に見えるかもしれません。
しかし、その裏側には見落とされがちな「コスト」「リスク」「柔軟性の欠如」といった問題点が潜んでいます。
特に、東京と地方都市部を結ぶ中長距離輸送においては、その影響がより顕著に現れます。
社員ドライバーの雇用コストと固定費
自社でドライバーを雇用するということは、給与以外にも多くの固定費が発生することを意味します。
代表的なものとして以下のような項目が挙げられます:
- 社会保険・厚生年金の企業負担
- 賞与・退職金・有給休暇などの福利厚生費
- ドライバーの労務管理や教育にかかる人件費
これらは毎月確実に発生する固定費であり、配送需要が少ない月でも変動しないため、経営を圧迫する要因となります。
車両維持・管理コストと事故リスク
配送業務において不可欠な車両の管理にも、下記のようなコストやリスクが伴います。
| 項目 | 具体内容 |
|---|---|
| 車検・整備費 | 法定点検・オイル交換・タイヤ交換などの費用 |
| 保険料 | 任意保険・自賠責保険などの継続的支払い |
| 事故対応 | 事故時の修理・代車手配・被害者対応など |
特に事故発生時には、ドライバーの休職や業務停止といった直接的な業務支障に加え、企業イメージの低下という重大なリスクも内包しています。
繁忙期・閑散期に対応しにくい柔軟性のなさ
自社ドライバー体制では、急な配送増加やルート変更に対応しづらく、繁忙期には人手不足、閑散期には稼働率の低下という課題が発生します。
これにより、
- 本来なら回避できるはずの外注コストの発生
- スタッフの過労による離職リスク
- 配送の遅延やミスによる顧客満足度の低下
など、ビジネス全体への影響も大きくなります。
東京⇔地方都市部の輸送は、距離と時間の制約が大きい分、これらの問題がより顕在化しやすくなるため、早めの見直しが求められます。
軽貨物配送に切り替えることで得られる3つのメリット
東京⇔地方都市部の配送業務を、自社ドライバー体制から軽貨物配送へ切り替えることで得られるメリットは非常に大きく、しかも多方面にわたります。
特に「コスト削減」「柔軟性向上」「雇用リスクの回避」は、企業経営の安定化に直結する要素です。
社会保険・福利厚生費を削減できる
自社で配送ドライバーを雇用する場合、社会保険・厚生年金・労災・雇用保険など、法定福利費の企業負担が不可避です。
また、交通費・有給・賞与・退職金・制服費用など、見えにくい間接コストも重くのしかかります。
一方、軽貨物業者に配送を委託することで、これらの福利厚生コストをすべて排除することができます。
契約ベースで稼働してもらうため、必要な日数・必要な距離に応じて費用を調整でき、完全な変動費化が可能です。
車両コスト不要・メンテ不要で固定費圧縮
軽貨物業者が所有・運用する車両を活用することで、自社での車両保有は不要となります。
これにより、以下のコストを完全にカットできます。
- 車両購入費(リース・ローン)
- 法定車検・整備・点検・保険料
- 事故・トラブル時の損害補填や代車対応
特に地方都市部への中長距離輸送では、車両の負荷も大きく、車両管理の手間も増加しがちです。
これらをアウトソースすることで、固定費から完全に解放されるという利点は極めて大きいと言えます。
繁閑に合わせて「必要な分だけ」使える効率性
軽貨物配送の最大の利点は、必要なときに、必要な台数・人員を稼働させられる柔軟性にあります。
具体的には以下のような運用が可能です。
| 配送ニーズ | 活用例 |
|---|---|
| 週1〜2回の定期便 | 地方店舗や工場への商品・部品配送 |
| 繁忙期だけの臨時便 | イベント出展・セール期間の在庫補充 |
| 夜間・早朝のみの特殊便 | 現場納品や施設向け時間指定納品 |
このように、人員過剰や車両遊休によるコスト無駄を完全に回避できることが、軽貨物活用の大きな魅力です。
また、複数都市・複数箇所への多拠点配送にも対応しやすいため、業務の最適化も図れます。
「配送を外注化する=コスト増」ではなく、「無駄な固定費を削減し、必要なときにだけ使える=最適化」という視点が重要です。
東京⇔地方都市部での軽貨物輸送の事例と導入パターン
軽貨物配送はスポット便だけでなく、東京と地方都市部を結ぶ中長距離輸送においても多くの企業が導入しています。
その背景には、人件費の削減だけでなく、配送品質の安定化や時間帯の柔軟性確保といったニーズがあります。
毎日定期便として導入するケース
例えば、東京都内の本社から地方工場や店舗へ毎日商品を届ける必要がある企業にとって、社員が交代制で長距離を運行する体制は負担が大きく、管理も煩雑です。
そこで、軽貨物チャーター便を利用した「平日毎日の定期配送」に切り替えることで、以下のようなメリットが実現できます:
- 朝積み → 昼前に納品 → 午後空車返却(1日完結型ルート)
- 同じドライバーが専任で担当するため品質が安定
- 人件費・車両コストの外注化で固定費が変動費化
ルート・荷量が決まっている業務には、定期契約便が最適です。
週3回など曜日指定で利用するケース
週3回、または火・木・土など曜日を指定した不定期ルート配送
軽貨物業者を利用すれば、必要な曜日にだけドライバーと車両を手配可能。これにより、
- 自社リソースの空き時間活用
- 無駄な人件費と時間外労働の回避
- 荷量に応じた車両手配が可能
など、柔軟な運用が可能です。
路線便では対応できない特別ルート対応
大手路線便では対応できない以下のような要件にも、軽貨物チャーター便は柔軟に対応できます:
| 要件 | 軽貨物での対応例 |
|---|---|
| 時間指定納品(午前9時必着など) | 早朝出発で地方現場に時間通り納品 |
| 荷扱いが特殊(精密機器・医療機器) | 専任ドライバーが丁寧に対応・専用台車で運搬 |
| 受取先の柔軟対応(立会・設置あり) | 指定現場での開梱・配置作業も含めた運用 |
軽貨物業者なら、単に「運ぶ」だけでなく、「届け方」までカスタマイズできるという点が大きな優位性です。
このように、東京⇔地方都市部の配送ニーズに応じた多様な活用モデルが可能であり、各企業の業種・荷物特性・運行頻度に合わせて最適な運用が組めるのが軽貨物委託の強みです。
自社配送から切替える際のチェックポイントと注意点
軽貨物配送への切替は、業務効率化とコスト削減に直結する反面、導入の過程でいくつかの重要な検討項目があります。
失敗しないためには、自社の配送ニーズと外部業者の提供内容を正しく把握し、段階的に移行することがポイントです。
荷物の種類・量に応じた委託の向き不向き
まず確認すべきは、自社が扱う荷物の特性が軽貨物委託に適しているかどうかです。
| 荷物の特徴 | 軽貨物委託の可否 | 対応策 |
|---|---|---|
| 小型・軽量(食品、雑貨、書類など) | ◎ 非常に適している | 軽バンで効率運搬 |
| 精密・割れ物(医療機器、精密機器) | ◎ 委託可(丁寧な取り扱いが条件) | 専任ドライバー・専用梱包 |
| 大型・重量物(什器、機材、家具) | △ 内容により要相談 | 2名体制・昇降機付き車両の手配など |
軽貨物配送は「350kg未満・荷台1.8m程度の積載」に最適なため、それ以上の物量がある場合は複数台対応やスポット混載の併用が必要です。
委託先のドライバー品質管理体制の確認
軽貨物は業務委託(請負)契約の形態が多く、ドライバーの品質=配送品質に直結します。
そのため、以下の点を必ず確認しましょう。
- 契約ドライバーの身元確認や教育体制があるか
- 服装・接客態度などのマナー指導がされているか
- 配送状況のトレーサビリティ(GPS・連絡体制)が整備されているか
信頼できる業者であれば、自社専任ドライバーとしてブランドを担う意識を持って対応してくれます。
導入初期は「併用」からの切替が安心
完全な切替に不安がある場合は、一定期間「併用運用」で比較検証を行うのがおすすめです。
例えば:
- 月曜・水曜は自社配送、火曜・木曜は軽貨物委託
- 繁忙期のみ軽貨物に切り替えて運用
このように段階的に導入することで、業務フローや社内体制に負荷をかけず、スムーズな切替が可能となります。
また、委託の実際の品質やコスト感も体感でき、継続判断がしやすくなります。
「一気に全部変える」のではなく、「現場の納得感を持って徐々に変える」ことが、成功の鍵です。
軽貨物配送で利益率アップに成功した企業事例紹介
実際に軽貨物配送を導入し、自社配送からの切替によって「利益率向上」や「業務効率改善」を実現した企業の事例をご紹介します。
現場での導入プロセスや結果から、多くの企業が抱える課題をどう解決したのかが明確に見えてきます。
【事例①】週5便を外部委託→月間40時間の拘束時間削減
東京都内の食品メーカーA社では、地方都市の物流倉庫へ毎日自社ドライバーで商品を運んでいました。
1日1往復に5時間以上を要し、月間合計で約100時間の拘束時間が発生。ドライバーの負担や残業代が課題となっていました。
軽貨物業者に定期チャーター便として週5回を外注したところ、ドライバーの労務負担は激減。
その結果、
- 他の配送業務に人員を再配置でき生産性が向上
- 残業代の支払いが減少
- 車両も1台減車し、車両コストを大幅に削減
配送時間の最適化と人件費削減の両立に成功した好事例です。
【事例②】車両2台分を委託→人件費と整備費を半減
B社は、東京の本社から関東・中部の各営業所へ複数車両で定期配送を行っていました。
しかし、整備費・燃料費・任意保険料などの維持コストが重く、車両稼働率も低下傾向に。
軽貨物配送へ委託したことで、年間維持費のかかる2台の車両を廃止。その結果、
- 人件費と整備費のトータルコストを約50%削減
- 自社社員を営業・倉庫業務へ再配置し効率化
- 必要に応じて繁閑調整できる柔軟体制を確立
固定費から変動費への転換で、経営体質の改善に直結しました。
【事例③】繁閑調整型の配送契約→配送効率が15%向上
C社では、季節商材を取り扱う業態のため、配送量が月によって大きく変動していました。
自社便では繁忙期は外注手配、閑散期は稼働率低下というジレンマを抱えていました。
軽貨物委託で繁忙期は毎日5台、閑散期は週2台という契約形態に変更。これにより、
- 配送量に応じた適正な費用支出を実現
- 配送の無駄を削減し、効率が15%向上
- 在庫移動のタイミングも調整しやすくなった
流動的なニーズに強く対応できる仕組みを構築できた好例です。
これらの事例が示す通り、軽貨物配送の活用は単なる「外注化」ではなく、「経営戦略の一環」として位置づけることが重要です。
まとめ:本当に「自社配送」である必要はありますか?
東京⇔地方都市部の配送を、自社ドライバーと車両で抱え込む時代は、終わりを迎えつつあります。
経済環境や人材不足、コスト圧迫の波の中で、従来の「固定費型」配送体制を見直すことは、今や多くの企業にとって避けて通れない経営課題となっています。
これまでの内容を振り返ると、軽貨物配送への切替により、以下のような改善が期待できます:
- 人件費・社会保険料・車両コストといった固定費の大幅削減
- ドライバー雇用リスク・事故リスクからの解放
- 繁閑に応じた柔軟な配送体制の構築
- 自社リソースを本業に集中できる体制へ移行
もちろん、配送ニーズや荷物の特性によっては自社運用が適している場合もあります。
しかし、もし今、「自社配送が負担になっている」「改善策を探している」という状況であれば、
「その配送、本当に自社でやるべきなのか?」
この問いを、今あらためて自社に投げかけてみてください。
私たち株式会社オーシャンズでは、企業の特性や配送頻度・荷物特性に応じた最適な軽貨物導入プランをご提案しております。
一部だけの委託導入から、全体の運用見直しまで、貴社の状況に応じてカスタマイズ可能です。
「配送部門をもっと軽く、もっと強く。」
その第一歩として、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
偉大な企業は、”変わること”を恐れません。
変化の先にあるのは、不安ではなく、可能性です。
あなたの会社の配送体制を見直すことで、得られるものは何でしょうか?
コストの最適化、人材の有効活用、そして、物流品質の革新。
私たちは「ただ運ぶ」だけの業者ではありません。
御社の物流に、新しい視点と新しい力を提供する「戦略パートナー」です。
今、この瞬間が、物流を変えるチャンスです。
さあ、一緒に「利益を生む物流」へ踏み出しましょう。